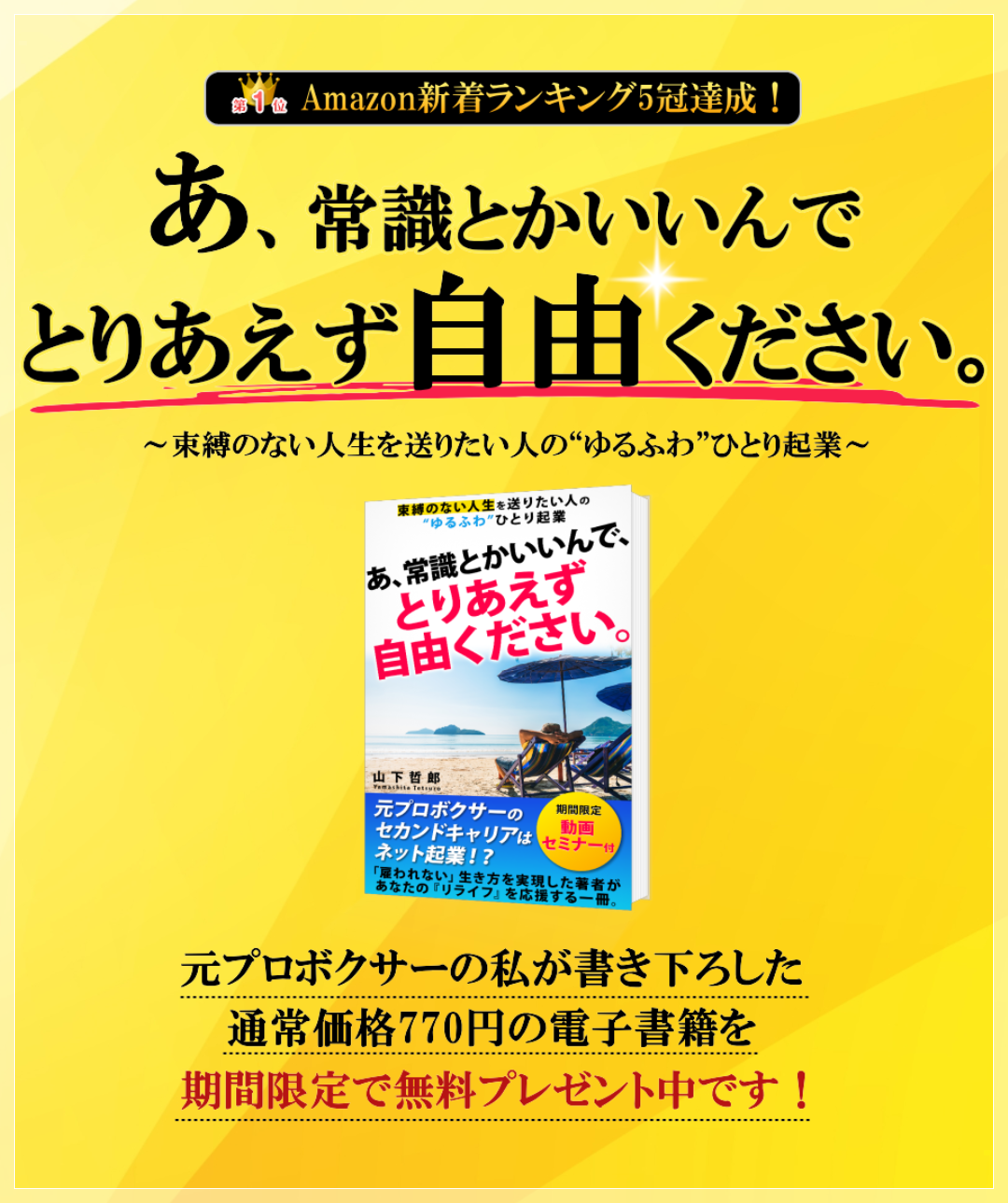てむ兄の自己紹介が短編小説になりました!(本人の肉声動画あり)

僕の自己紹介の物語を、小説風にアレンジして執筆してみました(笑)
また、これとは別に以下(もう1つの自己紹介)も力作です。
後ほどこちらのほうもぜひ!
⇒ 心底苦しかった過去が人生を考えるきっかけに…もう1つの自己紹介
…と、この小説の前に、まずは僕の肉声による自己紹介動画からご覧ください!
僕の肉声をお聞きになられていかがでしたか?(笑)
以下の小説も楽しめるはずですので、よかったらぜひ読んでみて下さい。
プロローグ
男の名は“カモガワ ハジメ”。
この物語の主人公だ。
その日の夕食は、大好物のハンバーグだった。
食卓には、ハンバーグの時のカモガワ家の定番メニュー、ポテトサラダとナポリタンも並んでいた。
夕食は毎日同じ時間に、決まって家族4人で食卓を囲んだ。
地方公務員の勤勉な父親エイジ、パートで働く真面目な母親クミコ、そして年の近い優しい兄マモル…。
カモガワ家は、どこにでもあるようなごく平凡な家庭に過ぎなかった。

そんな環境で育ったハジメの出身地は、九州は熊本県の山奥にある田舎町。
ごく平凡な家庭に生まれ育ったとは言っても、ハジメにはそれまでのカモガワ家の血筋からは想像できない不思議な側面が存在した。
一見すると、家庭環境に裏付けられた、寡黙で真面目で優しく大人しい性格の少年。
しかし、ハジメの生まれもった“価値観”だけに関して言えば、カモガワ家の歴史上始まって以来の、特別なモノを備えていたのである。
ハジメは、幼い頃から、とにかく人と同じことをするのが苦手な少年だったのだ。
どんな些細なことであっても、自身の信念を貫き、内に秘めたアイデンティティを大切にしていた。
とは言っても、決して“堅物”といった印象はまるでなく、友人たちはみんなしてハジメを慕い、周囲の大人たちをも凌ぐ人望を集めるような存在だった。
「人あたりが良くて接しやすい」
それが、友人たちの多くが抱く、ハジメに対する印象だった。
ハジメ自身も、争いごとが大嫌いで、八方美人な性格を備えていることを自覚していた。
そんなハジメのこだわりは一点だけ。
“自分の人生だけは自分でデザインする”ということ。
普段は温厚で、人当たりの良いハジメも、そんな自身の思い抱くアイデンティティに関してだけは、断固、汚されることを拒んだ。
でもなぜ…。
協調性がなく我が道を行くタイプであったハジメが、友人たちから慕われるような存在だったのか?
それは、ハジメが他人の価値観を全力で尊重し、決して否定をすることがなかったから。
自身の価値観に干渉されることだけには敏感だったが故、昔からハジメには、他人の人生を全力で応援する才能が備わっていたのだ。
誕生
なかなか産声をあげない…。
…。
やっぱり駄目だったか…。
辺りには半ば諦めめいた思いも交錯した。
覚悟はできていたとは言え、周囲に緊張が走る…。
…。
…。
…。
しかし…。
…。
…。
…。
次の瞬間…。
生まれた赤ん坊は、ようやく産声をあげたのだった。
割れんばかりの大きな大きな産声だった。
エイジとクミコは、間をおいて安堵の涙を流し、赤ん坊の無事に歓喜した。
生命の危機にさらされながらも、何とか無事にこの世に誕生したその赤ん坊は、ハジメと命名された。
なんとか一命をとりとめたハジメではあったが、その成長は、決して“スクスク”と呼べたものではなかった。
超未熟児で誕生し、人一倍カラダも小さく、心も弱かった。
ハジメには、幼少期の思い出が、ベッドの上の記憶しかない。
通っていた保育園を年間の半分以上休むほど、病弱だったのだ。
いつしかハジメは、強さに憧れ始めた。
やがて小学生になったハジメのヒーローは、ジャッキー・チェンだった。

エイジとクミコはそんなハジメを見て、少しでもたくましくなってほしいとの願いを込めて、少林寺拳法を習うよう勧めてみた。
告げられたハジメは、興奮を抑えられなかった。
「この僕が…憧れのジャッキー・チェンに近づける!」
強さを手にした未来の自分の姿を想い、辺りをピョンピョン飛び跳ねて喜んだ。
小さなカラダをいっぱいに使って喜びを表現したその様は、滑稽にすら思えた。
それから毎日近所の体育館へ通い始めたハジメだったが、意外にも自身の秘めたる才能に徐々に気付き始めるようになった。
小学3年生にして…なんと地区大会で最優秀賞を受賞するほどの実力になっていたのだ。

程なく県大会で優秀賞、さらに4年生時には全国大会でベスト16と、どんどん頭角を現すようになっていった。

それでも少林寺拳法の実力とは裏腹に、相変わらず、小さく病弱なカラダはまだまだハジメを苦しめていた。
たった1つの価値観
「ハジメー!お前にお菓子あげるよぉ!」
クラスの男子はみんな“ビックリマンシール”に夢中だった。

一世風靡している流行に取り残されまいと…。
本来はチョコのおまけで附属しているシール。
ところが、友人たちはみんなチョコそっちのけで、シール収集に夢中になっていた。
ハジメは、特に甘いものが好きなわけではなかったが、気を遣って、これをありがたく頂いていた。
ハジメは、周囲が熱をあげているビックリマンシールというものの魅力が、イマイチ理解できずにいたのだ。
野球少年だったハジメにとって魅力なのは、ビックリマンシールではなく、プロ野球選手カードだった。

“野球チップス”なるポテチのおまけで付いてくるカード。
これこそがハジメにとっては宝物だった。
ミニ四駆、たまごっち、ゲームボーイ…最近で言えば、妖怪ウォッチ…。
ハジメの目にはそれらは特に輝いては見えなかった。
イチローの活躍だったり、松井の活躍だったり…ハジメにとって重要なのは、専らそんな情報だったのだ。
ハジメは夏休みが大好きだった。
朝から高校野球が放送され、夜はナイターにかじりつく。
大好きな野球に囲まれた毎日は、まさに天国でしかなかったのだ。
チビの憧れ
どこからともなく『ギザギザハートの子守歌』を口ずさむ声が聴こえてきた。
遠くから断片的に聴こえてくるその歌声は、どうやらハジメのことをからかった替え歌のようだった。
“ちっちゃなころからちぃさくてぇ 中2で小5とよばれたよぉ…”
…。
ハジメよりもひと回り大きなカラダの同級生たちが、愛嬌を込めてそんな歌を歌っていたのだ。
中学生になったハジメは、父親の転勤で熊本市に引っ越していた。
少年から青年に変わる思春期の過程にあっても、取り残されたかのように、ハジメは相変わらず一人だけ、少年のカラダから脱せずにいた。
ハジメはとにかく強さに憧れた。
幼少期に憧れたジャッキー・チェンの強さに加え、男らしく優しく…強く…。
ハジメが思い描く“強い男”はそんな人間だった。
そんなある日、ブラウン管の向こうに、煌々と輝く男の存在を目の当たりにしたのだ。
ハジメが目にしたその男は、どうやらボクシングという競技をやっていたようだった。
文字通り、裸一貫、魂と魂をぶつけ合って闘う様に、ハジメはいつしか心奪われていった。
「ボクシングって…自身のイキザマを表現して勝負する競技だな…」
それがハジメが感じた率直な感想だった。
ハートの奥から湧き起こってくる熱い思いは、ハジメが生まれて初めて感じる感情だった。
「強いって一体どんな気分だろう?」
青いスパンコールの施された白いトランクスを穿き、しのぎを削る挑戦者の日本人を見ながら、ハジメの熱い思いは、次第に憧れへと変わっていった。
リング上で輝くその男は、どうやら父子家庭で育ったらしかった。
実家の岡山でテレビ観戦をしているという病弱の父親、そして、会場に駆けつけている結婚したばかりの妻、さらには、その妻のお腹に宿った新しい命…。
支えられている身近な存在を背負って闘う男の姿は、ハジメの目には、強く美しく映った。
そしてその挑戦者の日本人はその日、日本ボクシング界の史上最速記録で世界チャンピオンに君臨したのだった。
「ボクシングかぁ…。いつか趣味でいいからやってみたいな…。高校まで野球に打ち込んで甲子園に行って…。そしたらボクシング…やってみっかな…。カッコいいよな…」
その夜、ハジメは漠然とした思いにふけった。
大きな主張
「僕は甲子園に行くんだ!」
ハジメの中学時代は野球漬けだった。
カラダの小さなハジメは先輩や同級生の中に入ると、まるで大人の中に一人チビッ子が紛れ込んでいるようだった。
それでも、ハジメは中学2年生になると、上級生に混じって、ベンチ入りを果たすようになっていった。
決して人一倍ズバ抜けたセンスがあったわけではなかったが、人一倍の努力だけは怠らなかった。
ハジメは、もはや野球の為だけに生きていた。
甲子園以外は見えていなかったのだ。

中学3年生の高校受験の時期を迎えた。
ハジメは当然のように、地元の甲子園常連校であった実業高校への進学を希望していた。
そして、その旨を両親と担任教師のヤギに伝えた。
しかしどういうわけか…
エイジもクミコも、そしてヤギも、さらには、噂を聞きつけた野球部の顧問教師だったシノダまでも…
ハジメの志望高校に対し、口を揃えてみんなが反対したのだ。
「進学校に行くべきだ」と。
真面目だったハジメの成績が、中途半端に良かったことが理由だった。
将来のハジメの可能性を考えた場合に、大人たちの主張は、当時で考えれば、ごく当然の一般的な意見だったのかもしれない。
しかし、もちろんハジメは、全くもって聞く耳を持たなかった。
そればかりか、珍しく猛烈に反発した。
そう…ハジメは昔から、自分の思い描く人生に干渉されることだけには、どうしても耐えることができない人間なのだ。
そんなハジメの姿を、それまでに見たことが無かったヤギとシノダは、驚きを隠せないでいた。
…。
話は平行線をたどったまま、一向に進まない。
…。
そんな中、ハジメは誰もが想像だにしなかった構想を練り始めたのだ。
ハジメにとって、思い付く打開策は1つだけだった。
大人達の“進学校であることが条件”という主張を飲むには
「もはや地元の高校じゃ解決しない」と。
そして、自ら全国に存在する高校を調べまくったのだ。
つまり、進学校でありながら、甲子園常連校でもある高校を、全国から探し出し始めたのだった。
程なくして、同じ九州内の福岡県福岡市に存在する、私立高校にターゲットを絞った。
しかし、ハジメは、前回のように大人たちから理屈で説得されることを懸念して、その事実は誰にも伝えなかった。
それどころか、ハジメ自らその高校に電話を入れ、願書を請求したのだった。
そして数日後、自宅に届いた願書を1人書き上げた。
ハジメは書き終えた願書に、保護者のサインをもらう段階になって、初めて一連の流れと、自身の思いを、エイジとクミコに告げた。
…が、エイジもクミコも、予想に反して、さほど驚かなかった。
ハジメは、若干拍子抜けしてしまった…。
当然だが、エイジもクミコもハジメの性格をよく知っている。
生まれた時から…それこそハジメが物心つく前から…毎日顔を合わせているのである。
もはや、ハジメ自身よりもハジメのことを理解している。
エイジもクミコも、ハジメが何かを企んでいることは、すでに薄々と感じとっていたのだ。
それは親として、当然の姿だった。
2人は決して賛成こそしなかったが、覚悟は決めていたようだった。
ハジメの思いを尊重し、旅立ちを応援する準備はすでに整えていたのだった。
驚いたのは、担任のヤギと野球部顧問のシノダだった。
それまでの教師人生で、そこまでして大人たちに自分の信念や主張を押し通す生徒を、見たことがなかったのだ。
…。
波乱の中学3年生の冬、ハジメは高校受験に合格し、春になると1人、福岡へと旅立った。
小さな誇りと虚無感
15歳にして早くも親元を離れ、寮生活を送ることになったハジメは、幼少期からの念願だった、ホンモノの野球を目の当たりにした。
毎日がまさに野球漬けである。
それでも、これまでに体験したことがないハイレベルな野球環境に、喜びを実感していた。
日々、ワクワクの連続に胸が躍った。
集結した精鋭たちの一員として、同じ環境に身を投じている自分が、誇らしくもあった。
しかしながら、唯一、ハジメを苦しめ抜いたことがあった。
…。
…。
…。
体育会系の理不尽な上下関係。
…。
野球部のそれは、特に際立っていた。
ハジメは理解できずにいた。
“白”でも先輩が“黒”と言ったら“黒”。
寮生活を送っていたハジメには、24時間365日、プライベートな時間なんて、まるで存在しなかった。
部活動内だけではなく、私生活でも、常に上から監視され、命令の声が飛び、理不尽な注文や体罰を受ける。
まさに奴隷という言葉がピッタリだった。
そこには、ハジメが大切にしていたアイデンティティの居場所は存在しなかった。
次第にハジメは自問自答を繰り返すようになっていった。
「僕は本当に野球が好きなんだろうか…本気で野球を愛しているのだろうか…」
次第に身も心もズタボロに憔悴しきっていった。
…。
…。
…。
入学して1年が過ぎた。
高校野球を始めて1年が過ぎたのだ。
単身福岡での寮生活も1年。
「3年生は神様、2年生は一般人、1年生は奴隷」
そんな伝統の下、高校生活2回目の春が到来した。
ハジメの1年生終焉の時期である。
…。
…。
…。
2年生に進級して、後輩たちが入部してきた。
しかし、ハジメは受け継がれてきた野球部の伝統を、自分だけはどうしても受け継ぎたくなかった。
自分の前にいつも立ち塞がっていた先輩たちのような存在には、絶対になりたくなかった。
そして…ハジメは大きな決断をした。
…。
…。
…。
あれほど夢見ていた甲子園出場を諦め、野球部の退部を決心したのだ。
あれほど愛した野球を捨て、自ら逃げたのだ。
考えに考えて出した決断とはいえ、ハジメは自分が情けなくて仕方がなかった。
何より、あれほどのわがままを受け入れてくれた両親に対して、心から申し訳ない気持ちでいっぱいだった。
それまで甲子園だけを目標に生きてきたハジメは、残りの高校生活には、夢も希望も失い、自分が何の為に生きているのか、自問自答を繰り返した。
裸一貫
特に将来を考えるでもなく、ハジメは大学へ進学し、これといった生きる目的もなく、淡々と…淡々と…何の変哲のない毎日を送っていた。
周囲の人間は、サークルだの合コンだのと…新たな環境に浮かれているようだった。
しかし、そんな大学生活に、ハジメはなかなか馴染めなかった。
「なんでみんなあんなに楽しそうにしているんだろう?」
「なんでみんなあんなにイキイキとしているんだろう?」
ハジメは、周囲の人間が羨ましくもあると同時に、反面、自分はそうではなくてよかったと安堵を浮かべてもいた。
…。
刺激が欲しかった。
心から魂を燃やせる刺激が…。
…。
…。
…。
そんな時、ふと…あの時を思い出したのだ。
「ボクシングかぁ…。いつか趣味でいいからやってみたいな…。」
そう一人ごちたあの日、ブラウン管越しに観たあの男の姿が、鮮明に蘇ってきた。
時を経て、あの時の男は日本ボクシング界のカリスマとして崇められ、日本人離れしたセンスと、歯に衣言わせぬ言動、そして独特の価値観を通して人々を魅了していた。
ボクシングを意識し始めた時、ハジメがこの男の生き様に魅了されるのは、もはや必然でしかなかった。
新たな挑戦に胸を躍らせたハジメは、思い立ったが吉日、自宅から一番近いボクシングジムに通い始めた。
少年時代に習っていた少林寺拳法とは、まるで勝手が違った。
毎日教わる新たな技術の取得や、メンタルトレーニング、体力トレーニング…練習を終えるとクタクタで疲労困憊だったが、その疲労感が妙に心地よかった。
そして、そんな充実した毎日が嬉しくもあった。
ハジメは、たちまちボクシングの魅力の虜になっていった。
野球を諦めて以来、ようやく人生に生き甲斐を見出すことができた。
ボクシングの奥の深さ、難しさ、世界観にどっぷりハマってしまい、ハジメは程なく、本格的にプロになることを決意した。
嘘の通用しない世界で、文字通り“裸一貫”の自分で勝負したい思いが募っていった。
何より、プロボクサーという生き方に…いや…むしろ、中学生の時にブラウン管越しに観た、あの男の生き様に魅了されていた。

大学3年生も中盤以降になると、周囲は就職活動を始めたが、ハジメは、周囲の忠告にも一切耳を貸すことなく、我が道を歩んだ。
プロボクサーとして生きる道へ、揺るぎない思いを、真っ直ぐに貫いた。
大学を卒業したハジメは、満を持して、日本ボクシングコミッションのプロテストに合格し、晴れてプロデビューを飾った。
福岡でプロデビューを果たしたハジメは、程なくボクシングジムを移籍することになり、活動の拠点を東京へと移した。
9割9分は辛く苦しい思いばかりを重ねたが、勝利した際の残り0割1分の喜びは、100倍にも1000倍にもなって跳ね返ってきた。
その瞬間だけの為にボクシングをやっていると言っても過言ではなかった。
誰しもが味わうことができるわけではないその喜びは、ハジメにとって貴重な財産になった。
こうしてハジメは10年間、プロのリングに身を捧げ…いや、自身の命を捧げて生きた。
ハジメにとっては、リング上こそが、自己表現の場所であり、自分の存在証明の場所だったのだ。

生きた証し
プロボクシング人生を引退したハジメは、次の人生を模索していた。
他人の決めたルールの中で生きることには、人一倍窮屈な感情を抱いてしまうハジメの中には、就職という選択肢は皆無で、何かしらの事業を自分でやりたいと考えていたのだ。
自分の人生を自分でデザインして生きる上で、就職という選択は、真逆の道だと考えたからだった。
【参照】パワハラ撲滅!承認欲求を満たしてこその人望!リーダーよ、お聞きなされ!
そしてそれは正解だった。
ネットビジネスの存在を知ってそれは確信に変わったのだ。
ネットビジネスを知れば知るほど、大いなる可能性を感じ始め、失敗を重ねながらも、徐々に結果を残せるようになっていった。
自らの経験から、このビジネスが多くの人を救えると感じたハジメは、現在、ライフデザインコンサルタントとして活動している。
思えば、ハジメの人生の信念は、ずっと一貫している。
「この世に生きた証しがほしい」
野球に打ち込んだことも、ボクシングに命をかけたことも、ネットビジネスにハマったことも…。
だからハジメは今、コンサルタントという人生を自らに課せられた使命だと感じているのだ。
自身が生きたことを証明できるのは、自身に関わった人間だけ。
ハジメは、この世を去るときに、いったい何人の人間が、自分との別れを惜しんでくれるのかを考えるようなった。
それこそが自身がこの世に残した、価値のバロメーターだと考えているからだ。
ハジメに関わった人間がハジメに対して抱く“感謝の量”こそがまさにそれだと感じている。

ハジメはたくさんの「ありがとう」に囲まれて生きたいと望んでいるのだ。
いつ日かこの世を去るときが訪れても、笑っていたいと望んでいるのだ。
この先、そんな素敵な人生を送れたら最高に幸せだと思っている。
さらに「もう1つの自己紹介 ~あの時の苦しみを経て~」を作りました。
力作です。